実はやわらかい法律〜進化する科学技術と法律との関係とは〜【ひふみ目論見倶楽部 専門分野編#6 稲谷 龍彦さん】
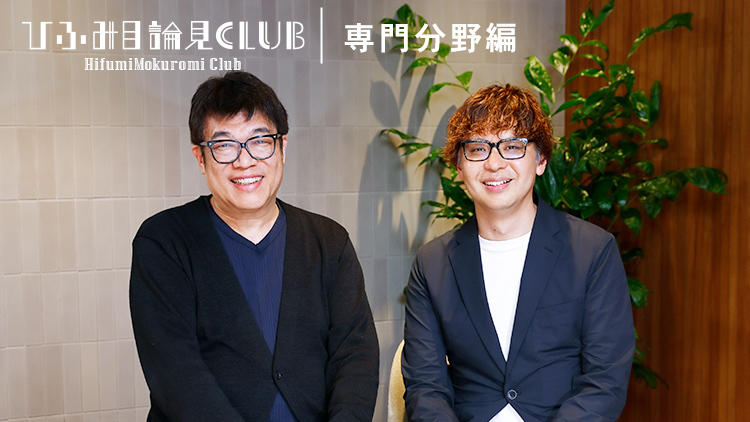
成長産業を提示し、10年後の未来を創造する「ひふみ目論見倶楽部」。今回は、京都大学大学院法学研究科教授の稲谷龍彦氏をお招きし、科学技術と人間との共存を目指す「Society5.0」の実現を見据えた、法や倫理の在り方についてお話しいただきました。稲谷教授の講演と、講演後に行なわれた座談会の様子を一部抜粋して紹介します。
ひふみ目論見倶楽部とは?
「ひふみ目論見倶楽部(愛称:ミーモ)」は、未来の選択肢を提示し創造することを目指して設立しました。「目論見倶楽部」という名前は、未来を企画して前進し世の中を動かしていくというニュアンスを「目論む」という言葉に込めて名付けました。 ひふみが提示する新しいアクティブファンドの在り方、そして「ひふみの魅力」を形づくる中核的な活動が、この「ミーモ」です。レオス・キャピタルワークスのメンバーや外部の専門家を中心とした学術的な活動を通して、10年先を見据えてひふみの運用に落とし込むことや、より多くの人を巻き込んだコミュニティや勉強会として機能することを目指します。
稲谷 龍彦さん プロフィール
京都大学法学研究科 法政理論専攻刑事法講座 教授 東京大学文学部卒、京都大学大学院法学研究科助教、パリ政治学院法科大学院客員研究員、シカゴ大学政治学部客員研究員、特定国立研究開発法人理化学研究所・革新知能統合研究センター客員研究員を経て、2019年より京都大学大学院法学研究科教授。専門は刑事学で、グローバル化する企業犯罪や科学技術と法規制のあり方について研究している。著書に『刑事手続におけるプライバシー保護 -熟議による適正手続の実現を目指して-』(弘文堂)、松尾陽編『アーキテクチャと法』(弘文堂)がある。
科学技術と共進する法を求めて
多様化するリスクに どう対応するか
科学技術の進化はまさに日進月歩。そこで課題となっているのが法の整備です。テクノロジーと人間の共存を目指す、いわゆる「Society5.0」の実現に向けて、法や倫理にはどのような対応が求められているのでしょうか。まず必要なのは、法整備の見直しです。従来の法律は「ウォーターフォール型」と呼ばれ、上の決定をトップダウン的に下ろしてきました。
しかし、自動運転技術や自律飛行ドローンなど、著しい発展を見せる科学技術を前に、全ての運用リスクをカバーすることが難しくなっています。そこで注目されているのが、「アジャイルガバナンス」という考え方です。その特徴は、「多層的に考える」ということ。意思決定のスピードに応じて意思決定プロセスを多層化し、複数の層に跨ってネットワークを形成するマルチ・ステークホルダーが協調して課題を解決することで、最終的には全体最適化された秩序が完成するわけです。 加えて、ロボットとの共生のために不可避なのが、人間にとってロボットをどう位置づけるかという議論です。Society5.0 が目指しているのは、何かしらの困難を抱える人が、技術の介入によってウェルビーイングな生活を手に入れる世界です。しかし、ロボットと一緒に暮らすということは、大量のプライバシーデータを引き渡すことでもあり、そのリスクに法や哲学も細かく対応していく必要があります。
アニミズムと「自律した個人」
ロボットを人間の「共生種」と位置づけることについては、文化圏によって反応が異なります。日本人は古来アニミズム信仰を持ち、『鉄腕アトム』や『ドラえもん』など、ロボットとの共生を描いたアニメ作品を見て育ったためか、ロボットに助けられたり、心を動かされたりすることに対し、特に疑問を持つことはありません。
しかし、西洋人は自分の意思は全て自身の内側から発露するものだという「自律した個人」という考えが強く、ロボットが人間の思考領域に介入することに大きな反感を抱きます。「自分の意思決定をロボットに任せるなんて、どうかしている」というわけです。このような世界観の違いを越えて、国際的に統一された法や倫理を考えるには、具体的な問題に絞った「不完全に理論化された合意」を形成し続けることが重要です。異なる思想の溝を埋めつつ、科学技術と法が共進化できる状態に持っていくことが、法というナラティブに求められている役割です。

技術と人間の相互作用で“生きづらさ”のない社会に
アニメがもたらす若者の可塑性
藤野:人間以外の生物を含む、全てのモノの中に魂が宿っているというアニミズムを信じる日本人と、「自律した個人」を信じる西洋人の考え方の違いは非常に興味深いですね。
稲谷:西洋人にとってのアニミズムは、ある種の偶像崇拝として忌避されがちですが、哲学者のアンディ・クラークは、人間の生物としての特性は、「拡張された心」にあると主張しています。つまり、人間は周囲の事物や環境を利用して、合理的な思考を発達させてきたわけで、事物を介さずに正しい判断ができるという「自律した個人」論は、人類の進化の歴史から見ても不自然な点が多いように思います。一方、2002年にノーベル経済学賞を受賞した経済行動学者のダニエル・カーネマンは、人間の意思決定には、直感的で自動的な「システム1」(速い思考)と、熟慮的で合理的な「システム2」(遅い思考)の二つの系統があることを指摘しました。この二つがうまく作用するおかげで、人間は正しい判断ができるわけですが、どちらのシステムにも得手不得手があり、外部要因によって簡単に判断を誤ることがあるという事実は頭に入れておくべきです。
藤野:私は趣味でピアノを弾くのですが、演奏時はまさにシステム1とシステム2のせめぎ合いだと感じます。指を動かしている間はほぼ無意識ですが、その一方で音のニュアンスに変化をつける際には、極めて理性的な動きが求められるからです。
稲谷:確かにそうですね。それに近い話ですと、ジャズは進行のルールが決まっていますが、そこをあえて逸脱することで、音楽に面白みが出ます。ロボットとの会話でも、想像していなかった反応がロボットから返ってくることを「面白い」と感じると、脳が刺激されるといわれています。その“面白み”は万国共通の感覚だと思うので、そこを足がかりに、異なる主張を持つ両者が歩み寄れるといいですね。
藤野:お話にも出てきた手塚治虫の『鉄腕アトム』、そして『火の鳥』は、日本人の価値観や宗教観が表れた象徴的な作品です。こうした作品が世界に発信されることの意義は大きいですね。稲谷 海外でプレゼンをした時にロボットとの共生に否定的な反応を示すのは、たいてい私と同年代かそれ以上の年代。日本のアニメを見て育ったであろう20~30代の若者は、「現実の世界にドラえもんがいたら便利だよね」というスタンスで、柔軟に受け入れてくれるのが印象的です。ロボットとの共生に西洋の若者が可塑性を持っているということは、対立する二つの価値観が、何らかの形で交わる未来もそう遠くないのではないかと感じます。

目指すは ウェルビーイングな社会
藤野:これからの10年間を考える時、ウェルビーイングは非常に重要なキーワードになると思うのですが。
稲谷:私も同感です。AIやロボットの力を借りて、今よりも国民一人ひとりが幸福を感じられる未来であってほしいと願っています。日本国憲法の中で、私が最も重要だと思っているのは、13条の幸福追求権です。これからの10年間は、それぞれの“幸福追求”をいかに具体化していくかがテーマになるのではないかと思います。
藤野:「成長戦略プロジェクト」で関わっている富山県もウェルビーイングの追求に力を入れています。富山県の平均世帯所得は全国5位と、比較的裕福な地域ですが、女性の県外流出が止まりません。彼女たちにとって富山はウェルビーイングな場所ではないから。さらなる地域発展を目指すためにも、お金や健康といったわかりやすい指標だけでなく、今なお残る男尊女卑的な価値観など、様々な“生きづらさ”を解消していく必要があります。
稲谷:一人ひとりの認知や行動に寄り添い“生きづらさ”を軽減するという目標は、Society5.0 において、科学技術が目指すところでもありますね。
藤野:今日の先生のお話を突き詰めていくと、全ては「人間像をどう捉えるか」というテーマに帰結するように感じます。技術で解決できるところは技術に頼りつつ、そうでないところでは、人間の在り方や、人と人との関係性を見つめ直すことが大切だと。国際的な法整備のアプローチについても同様です。いきなり正面突破を試みるのではなく、相手の背景を理解しながら、少しずつ合意を重ねていくことの重要性を認識することができました。
〈2025 年5月12日収録〉
※当記事のコメント等は、掲載時点での個人の見解を示すものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きや結果を保証するものではありません。ならびに、当社が運用する投資信託への組み入れ等をお約束するものではなく、また、金融商品等の売却・購入等の行為の推奨を目的とするものではありません。
同じタグの記事を検索
#ひふみ目論見倶楽部


